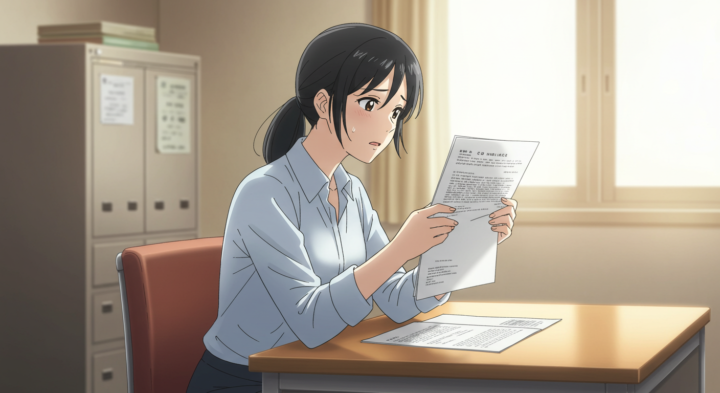定形外郵便って何?
2025年現在の料金はいくら?
値上げの歴史はどうなってるの?
そんな疑問を抱えているあなたにピッタリの記事です。
このページでは、日本郵便の定形外郵便の基本から最新料金一覧、そして過去から現在までの値上げの歴史を詳しく解説します。
ちょっとした雑学や、日常生活で役立つ裏ワザも盛り込んで、読んで楽しく、ためになる内容です。
特に2024年10月の大幅値上げ後の最新情報を反映しているので、個人利用からビジネス用途まで、定形外郵便を使う全ての人に役立つ情報が満載です。
定形外郵便って何?基本をサクッと解説
郵便物を送るときに「定形外郵便」という言葉を耳にしたことはありませんか?
でも、「定形郵便」と何が違うのか、実はよくわからないという人も多いですよね。まずはその基本からおさらいしてみましょう。
定形外郵便とは、日本郵便が扱う第一種郵便物の一種で、簡単に言うと「決まったサイズや重さに収まらない郵便物」のことです。定形郵便が長辺25cm×短辺17cm×厚さ1cm以内、かつ重さ50gまでという厳密な規格に当てはまるのに対し、定形外郵便はその規格を超えるもの。ただし、大きすぎたり重すぎたりする場合は別のサービス(例えばゆうパック)になるので、ある程度の範囲内で収まることが条件です。
具体的には、定形外郵便には「規格内」と「規格外」の2つのカテゴリーがあります。
- 規格内: 長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内、重さ1kg以内。
- 規格外: 規格内に収まらないもので、3辺の合計が90cm以内、最長辺60cm以内、重さ4kgまで。
例えば、手作りのアクセサリーを送るときや、少し大きめの封筒に入れた書類、厚みのある本など、日常で使うシーンは意外と多いんです。規格内と規格外で料金が異なるので、送る前にサイズを測っておくのが賢い使い方の第一歩ですよ。
2025年最新版 定形外郵便の料金一覧
さて、ここからは2025年2月時点の最新料金をチェックしていきましょう。2024年10月1日に大幅な値上げがあったばかりなので、旧料金と比較しながら見ていくと、どれだけ変わったかがよくわかりますね。以下に、規格内と規格外の料金をわかりやすく表にまとめました。
定形外郵便(規格内)の料金
| 重さ | 旧料金(2024年9月まで) | 新料金(2024年10月以降) |
|---|---|---|
| 50g以内 | 120円 | 140円 |
| 100g以内 | 140円 | 180円 |
| 150g以内 | 210円 | 270円 |
| 250g以内 | 250円 | 320円 |
| 500g以内 | 390円 | 510円 |
| 1kg以内 | 580円 | 750円 |
定形外郵便(規格外)の料金
| 重さ | 旧料金(2024年9月まで) | 新料金(2024年10月以降) |
|---|---|---|
| 50g以内 | 200円 | 220円 |
| 100g以内 | 220円 | 290円 |
| 150g以内 | 290円 | 380円 |
| 250g以内 | 340円 | 440円 |
| 500g以内 | 510円 | 660円 |
| 1kg以内 | 710円 | 920円 |
| 2kg以内 | 1,040円 | 1,350円 |
| 4kg以内 | 1,350円 | 1,760円 |
この表を見ると、値上げ幅が一目瞭然。規格内だと約20~30%、規格外だと最大30%近くアップしていることがわかります。特に重いものほど値上げの影響が大きいので、例えば1kgを超える荷物を送る人は、ゆうパックと料金を比較してみるのもいいかもしれませんね。
定形外郵便の値上げの歴史を振り返る
料金が上がったのはわかったけど、そもそもなぜこんなに値上げされるようになったのか、その背景を知るには過去を振り返るのが一番。ここでは、定形外郵便を含む郵便料金の値上げの歴史をたどってみましょう。
戦後からバブル期までの緩やかな値上げ
戦後間もない1949年、定形外郵便の料金は50gまで6円でした。当時の物価を考えると決して安くはないですが、生活必需品として郵便が使われていた時代です。その後、経済成長とともに少しずつ値上げが続き、1970年代には50gまで20円に。1980年代のバブル期には50円まで上がり、ここまでは比較的緩やかなペースでした。
1994年:消費税導入後の初の大改定
大きな転機となったのが1994年。この年、消費税が3%から5%に上がった影響もあり、定形外郵便の料金も50gまで80円に跳ね上がりました。約30%の値上げで、当時は「手紙が高級品になる!」なんて声も聞かれたそうです。この改定以降、しばらく大きな動きはなく、安定した時期が続きます。
2000年代~2010年代:小幅な調整の時代
2007年の郵政民営化後も、定形外郵便の料金は50gまで120円(2014年時点)と、20年間で40円しか上がっていません。この期間は電子メールやSNSの普及で郵便物の数が減り始め、逆にコストが上がっていくジレンマに直面した時期でもあります。でも、値上げは最小限に抑えられていました。
2024年10月:30年ぶりの大幅値上げ
そして迎えたのが2024年10月の大改定。定形外郵便の料金は規格内50gまで140円、規格外で220円に。これは1994年以来、約30年ぶりの大幅値上げです。背景には、人件費や燃料費の高騰、郵便物の減少による収益悪化があります。日本郵便によると、2023年度の郵便事業は686億円の赤字。このままではサービス維持が難しいということで、全国一律のユニバーサルサービスを守るための苦肉の策だったわけです。
値上げの裏側にある雑学とトリビア
ここからはちょっと視点を変えて、定形外郵便にまつわる面白い雑学やトリビアを紹介していきます。
雑学1:規格内の「3cmルール」の意外な落とし穴
規格内の厚さ3cmって、実は結構シビア。例えば、封筒にちょっと厚めの書類を詰め込むと、意外と3cmを超えちゃうんです。郵便局の窓口で「これ規格外ですね」って言われた経験、ありませんか?そんなときは、封筒を少し押して平らにしてみると、ギリギリ規格内に収まることも。ちょっとした裏ワザです。
雑学2:昔の郵便料金は「手紙1枚」単位だった?
戦前の郵便料金は、重さだけでなく「手紙1枚あたり」で計算されていた時期があったんです。たとえば大正時代は、1枚4銭。それが重さベースに変わったのは、効率化のため。今じゃ考えられないですよね。
雑学3:値上げ後もお得に送る方法
2024年の値上げで「もう定形外は高いだけ!」と思うかもしれませんが、実はまだお得な使い道が。例えば、500g以内の荷物を速達で出す場合、以前は定形外+速達の方がゆうパックより安かったんですが、値上げ後は逆転。でも、規格内で軽いものならまだまだ定形外がコスパいいですよ。料金比較を忘れずに!
定形外郵便を賢く使うためのコツ
料金が上がった今だからこそ、定形外郵便を賢く使う方法を知っておきたいですよね。ここでは、日常生活やビジネスで役立つコツをいくつか紹介します。
コツ1:サイズと重さを事前にチェック
規格内か規格外かで料金が違うので、送る前に定規とキッチンスケールで測るのが鉄則。特に厚さ3cmは要注意です。100均で買える簡易スケールでも十分なので、準備しておくと便利。
コツ2:他のサービスと比較してみる
1kgを超える荷物なら、ゆうパックやクリックポストの方が安い場合も。たとえば、クリックポストは全国一律185円(2025年時点)で、厚さ3cm以内ならお得。用途に応じて使い分けましょう。
コツ3:値上げ前の切手を使い切る
もし値上げ前に買った120円切手が余ってるなら、差額分の切手を貼れば今でも使えます。例えば、140円の規格内50gなら、120円切手+20円切手でOK。無駄にしない工夫も大事ですね。
定形外郵便と私たちの暮らし
最後に、定形外郵便が私たちの生活にどう関わってきたのか、少し考えてみましょう。メールやLINEが当たり前になった今、わざわざ手紙や荷物を送る機会は減りました。でも、誕生日カードや小さなプレゼント、ネットショップでの商品発送など、定形外郵便が活躍するシーンはまだまだあります。
値上げで「高くなったな」と感じるかもしれませんが、その裏には、全国どこでも同じ料金で届けられるユニバーサルサービスの精神が息づいています。都会も田舎も関係なく、手紙や荷物が届く安心感は、やっぱり郵便ならではですよね。
今後の値上げはあるのか?未来を予想
2024年の値上げで一息ついた日本郵便ですが、実はまだ赤字が続く見込み。総務省の試算では、2025年度は67億円の黒字になるものの、2026年度以降は再び赤字に転じる可能性が指摘されています。このままいくと、数年後にまた値上げがあるかも?なんて声もチラホラ。次はどんな料金になるのか、ちょっと気になりますね。
まとめ
定形外郵便の世界、いかがでしたか?2025年最新の料金一覧から、規格内・規格外の違い、値上げの歴史まで、たっぷりお届けしました。120円だった50g以内が140円に上がったり、30年ぶりの大改定があったりと、郵便事情も時代とともに変わってきています。でも、賢く使えばまだまだお得に送れる方法はあるんです。サイズを測ったり、他のサービスと比較したり、ちょっとした工夫で節約も可能。
この記事を参考に、定形外郵便を上手に活用してみてください。


![【母の日はいつ】日付の由来、世界各国の母の日、プレゼント選びのヒントまで徹底解説[2025年最新版]](https://mokuteki.net/wp-content/uploads/2025/02/1742299516-f38c530fff06434c5f84003d3f0bcb75-720x393.png)