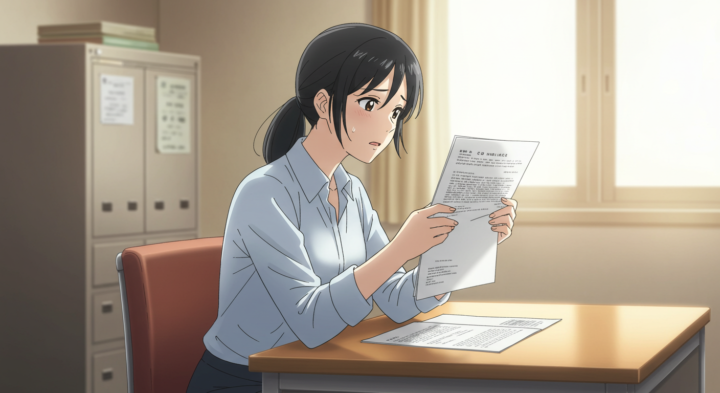「あれ、もしかしてインフルエンザ…?」高熱や関節痛、あの独特の倦怠感。風邪と似ているようで、実は全く違うインフルエンザ。
ここでは一般的な情報をまとめましたので参考にしてください。
症状がでている場合は、医師にしっかりとみてもらい、正しい判断を仰ぐことを忘れずに行いましょう。
インフルエンザと風邪との違いを比較
皆さん、こんにちは!「風邪かな?」と思ったら、実はインフルエンザだった…なんて経験、ありませんか? インフルエンザと風邪は、症状が似ているため、見分けるのが難しいこともありますよね。 でも、実はこの2つ、原因となるウイルスも、症状の出方も、そして治療法も全く違うんです!
インフルエンザウイルスとは?
インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することで起こる病気です。 このウイルスには、主にA型、B型、C型の3つの型があります。 中でも、私たちが特に注意しなければならないのが、A型とB型です。
- A型インフルエンザ: 最も流行しやすく、症状も重くなりやすいのが特徴です。 さらに、A型はウイルスが変異しやすいため、毎年のように新型が登場し、世界的な大流行(パンデミック)を引き起こすこともあります。 「H1N1」や「H3N2」といった型を聞いたことがあるかもしれませんね。
- B型インフルエンザ: A型ほどではありませんが、B型も流行することがあります。 症状はA型に似ていますが、比較的軽症で済むことが多いと言われています。 しかし、子どもや高齢者など、免疫力の低い方は重症化することもあるので、油断は禁物です!
- C型インフルエンザ: C型は、ほとんどの場合、軽い風邪のような症状で済むため、あまり問題になることはありません。 一度感染すると、生涯免疫が獲得できるとも言われています。
風邪との症状の違い
「風邪もインフルエンザも、熱が出て、咳が出て…同じじゃないの?」と思うかもしれません。 確かに、どちらも発熱、咳、鼻水などの症状が出ることがありますが、実は、症状の出方や重さに違いがあるんです!
| 症状 | インフルエンザ | 風邪 |
|---|---|---|
| 発熱 | 38℃以上の高熱が急激に出ることが多い | 微熱程度のことが多い |
| 悪寒・倦怠感 | 強く、全身がだるくなる | 軽い |
| 関節痛・筋肉痛 | 強く、全身の関節や筋肉が痛む | 軽い、またはない |
| 咳・鼻水 | 咳は、痰が絡むような湿った咳になることが多い。鼻水は、透明なものから、黄色っぽいものまで様々。 | 咳は、乾いた咳が出ることが多い。鼻水は、透明なことが多い。 |
| 頭痛 | 激しい頭痛が起こることがある | 軽い、またはない |
| 消化器症状 | まれに、吐き気や嘔吐、下痢などの症状が出ることがある(特に子ども) | ほとんどない |
| 発症時期 | 突然、症状が現れる | 比較的ゆっくりと症状が現れる |
| 症状の持続期間 | 1週間程度続くことが多い(解熱後も、咳や鼻水が長引くことがある) | 数日程度で治ることが多い |
インフルエンザの感染経路
インフルエンザウイルスは、どのようにして私たちの体に侵入してくるのでしょうか? 主な感染経路は、飛沫感染と接触感染の2つです。
- 飛沫感染: 感染者の咳やくしゃみによって、ウイルスを含んだ飛沫(しぶき)が飛び散り、それを吸い込むことで感染します。 飛沫は、1~2メートル程度飛ぶと言われています。
- 接触感染: 感染者が触れたドアノブや手すりなどに付着したウイルスに、私たちが触れ、その手で口や鼻、目を触ることで感染します。 ウイルスは、乾燥した環境では数時間~数日生き残ると言われています。
インフルエンザの流行時期
インフルエンザは、毎年冬になると大流行しますよね。 なぜ、冬に流行するのでしょうか?その理由は、主に以下の3つです。
- 気温と湿度の低下: インフルエンザウイルスは、低温・低湿度の環境を好みます。 冬は、気温が低く、空気が乾燥するため、ウイルスが活発になり、感染力も高まります。
- 免疫力の低下: 冬は、寒さや乾燥によって、私たちの体の免疫力が低下しやすくなります。 免疫力が低下すると、ウイルスに感染しやすくなります。
- 人が密集する機会の増加: 冬は、クリスマスやお正月など、人が集まるイベントが多くなります。 また、暖房の効いた室内で過ごす時間が増えるため、感染者との接触機会が増え、感染が広がりやすくなります。
【症状チェックリスト】こんな症状が出たらインフルエンザかも
「あれ?なんだか熱っぽい…風邪かな?」 そう思って放置していたら、あっという間に高熱!なんてこと、インフルエンザではよくあります。 ここでは、インフルエンザの典型的な症状から、見過ごしがちな初期症状、そして注意すべき重症化のサインまで、詳しく見ていきましょう。
初期症状:見逃さないで!インフルエンザのサイン
インフルエンザは、多くの場合、突然の発症が特徴です。 しかし、本格的な症状が出る前に、いくつかの「サイン」が現れることがあります。 これらの初期症状を見逃さず、早めに対処することが大切です。
- 悪寒(さむけ): 熱が上がる前に、ゾクゾクと寒気を感じることがあります。 これは、体がウイルスと戦うために、体温を上げようとしているサインです。 「寒いな」と思ったら、厚着をして体を温め、安静にしましょう。
- 倦怠感(けんたいかん): 体全体がだるく、力が入らない感じがします。 「なんだか体が重い」「何もする気が起きない」と感じたら、要注意です。
- 頭痛: ズキズキとした頭痛や、頭が重い感じがすることがあります。 市販の頭痛薬を飲んでも、なかなか良くならない場合は、インフルエンザの可能性があります。
- 関節痛・筋肉痛: 体の節々が痛んだり、筋肉が痛んだりすることがあります。 特に、腰や背中、太ももなどに痛みが出やすいと言われています。
- 食欲不振: 食欲がなくなり、何も食べたくなくなることがあります。 無理に食べる必要はありませんが、水分補給はしっかり行いましょう。
これらの初期症状は、風邪や他の病気でも起こることがあります。 しかし、「いつもと違う」と感じたら、無理せず休養を取り、様子を見ることが大切です。
特徴的な症状:インフルエンザ特有の症状をチェック!
初期症状に続いて、インフルエンザ特有の症状が現れてきます。 これらの症状が複数当てはまる場合は、インフルエンザの可能性が高いと考えられます。
- 高熱: 38℃以上の高熱が、急激に出ることが特徴です。 熱の上がり方は、個人差がありますが、39℃を超えることも珍しくありません。
- 関節痛・筋肉痛: 全身の関節や筋肉が、強く痛みます。 特に、腰や背中、太ももなどの大きな筋肉に痛みが出やすいと言われています。 「寝返りを打つのもつらい」「階段の上り下りがつらい」と感じることもあります。
- 咳: 激しい咳が出ることがあります。 最初は乾いた咳(コンコン)ですが、徐々に痰が絡む湿った咳(ゴホゴホ)に変わることがあります。
- 鼻水: 透明な鼻水から、黄色っぽい粘り気のある鼻水まで、様々な鼻水が出ます。
- のどの痛み: のどがイガイガしたり、ヒリヒリしたりすることがあります。 食べ物や飲み物を飲み込むときに、痛みを感じることもあります。
子どもの症状:大人と違う?注意すべきポイント
子どもがインフルエンザにかかった場合、大人とは異なる症状が出ることがあります。 特に注意すべきポイントは、以下の3つです。
- 熱性けいれん: 高熱によって、けいれんを起こすことがあります。 けいれんが起きた場合は、慌てずに、以下の対処をしましょう。
- 安全な場所に寝かせ、衣服を緩める。
- 嘔吐物に詰まらないように、顔を横に向ける。
- けいれんの様子を観察し、時間を測る(5分以上続く場合は、救急車を呼ぶ)。
- けいれんが治まったら、医療機関を受診する。
- 中耳炎: インフルエンザウイルスが、中耳に感染し、炎症を起こすことがあります。 耳の痛み、耳だれ、聞こえにくいなどの症状が出たら、早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。
- 消化器症状: 大人よりも、吐き気や嘔吐、下痢などの消化器症状が出やすい傾向があります。 脱水症状にならないように、こまめな水分補給を心がけましょう。
高齢者の症状:重症化しやすい理由は?
高齢者がインフルエンザにかかった場合、重症化するリスクが高くなります。 その理由は、主に以下の2つです。
- 免疫力の低下: 加齢とともに、免疫力が低下するため、ウイルスに感染しやすくなります。 また、感染した場合も、ウイルスを排除する力が弱いため、重症化しやすくなります。
- 基礎疾患の存在: 高齢者は、心臓病、糖尿病、慢性呼吸器疾患などの基礎疾患を持っていることが多く、これらの病気がインフルエンザによって悪化する可能性があります。
高齢者の場合、インフルエンザの症状が典型的でないこともあります。 「元気がない」「食欲がない」「いつもと様子が違う」といった、ちょっとした変化にも注意が必要です。
重症化のサイン:こんな時はすぐに病院へ!
インフルエンザは、まれに重症化し、命に関わることもあります。 以下の症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
- 呼吸困難: 息苦しい、呼吸が速い、ゼーゼーするなどの症状が出た場合は、肺炎や気管支炎を起こしている可能性があります。
- 意識障害: 呼びかけに反応しない、ぼーっとしている、意味不明な言動があるなどの症状が出た場合は、脳炎や脳症を起こしている可能性があります。
- 胸の痛み: 激しい胸の痛みや、圧迫感がある場合は、心筋炎や心不全を起こしている可能性があります。
- 脱水症状: 尿の量が少ない、口の中が渇く、皮膚が乾燥するなどの症状が出た場合は、脱水症状を起こしている可能性があります。
- 症状の悪化: 解熱剤を使っても熱が下がらない、症状がどんどん悪化する場合は、重症化している可能性があります。
これらの症状は、緊急を要するサインです。 迷わず、すぐに医療機関を受診しましょう。
インフルエンザの検査と診断
「インフルエンザかもしれない…」と思ったら、早めに医療機関を受診しましょう。 インフルエンザの診断には、主に迅速診断キットが用いられます。
迅速診断キットとは?
迅速診断キットは、鼻の奥の粘膜や、のどの粘膜を綿棒で拭って、インフルエンザウイルスがいるかどうかを調べる検査キットです。 検査時間は、10分~15分程度と短く、その場で結果がわかります。
検査の精度は?
迅速診断キットの精度は、100%ではありません。 特に、発症直後(発熱後12時間以内)は、ウイルスの量が少ないため、陰性となることがあります(偽陰性)。 そのため、症状からインフルエンザが強く疑われる場合は、時間を置いて再検査を行うことがあります。
病院に行くタイミング
インフルエンザの検査は、発症後12時間~48時間以内に行うのが最も良いとされています。 これは、抗インフルエンザ薬の効果を最大限に引き出すためには、発症後48時間以内に服用を開始する必要があるためです。
ただし、発症後48時間を過ぎていても、症状が続いている場合は、検査を受けることができます。 また、重症化のリスクが高い方(高齢者、基礎疾患のある方、妊婦など)は、早めに医療機関を受診しましょう。
何科を受診すればいい?
インフルエンザの疑いがある場合は、内科、小児科、耳鼻咽喉科のいずれかを受診しましょう。 かかりつけ医がいる場合は、まずかかりつけ医に相談するのが良いでしょう。
インフルエンザの治療法
インフルエンザと診断されたら、適切な治療を受けることが大切です。 治療法には、主に抗インフルエンザ薬による治療と、症状を緩和するための対症療法があります。
抗インフルエンザ薬
抗インフルエンザ薬は、インフルエンザウイルスの増殖を抑える薬です。 現在、日本で使用されている主な抗インフルエンザ薬は、以下の4種類です。
- タミフル(オセルタミビル): 飲み薬。1日2回、5日間服用します。
- リレンザ(ザナミビル): 吸入薬。1日2回、5日間吸入します。
- イナビル(ラニナミビル): 吸入薬。1回吸入すれば、治療が完了します。
- ゾフルーザ(バロキサビル マルボキシル): 飲み薬。1回服用すれば、治療が完了します。
これらの薬は、いずれも発症後48時間以内に服用を開始することで、効果を発揮します。 症状を軽減し、回復を早める効果が期待できます。
薬を飲むタイミング
抗インフルエンザ薬は、医師の指示に従って、正しく服用することが大切です。 熱が下がったからといって、自己判断で服用を中止しないようにしましょう。
自宅療養のポイント
インフルエンザにかかったら、自宅で安静に過ごすことが基本です。 以下の点に注意して、療養しましょう。
- 十分な睡眠: 体力を回復させるために、十分な睡眠を取りましょう。
- 水分補給: 発熱や下痢によって、脱水症状になりやすいため、こまめに水分補給をしましょう。 経口補水液やスポーツドリンクなどがおすすめです。
- 栄養補給: 食欲がない場合は、無理に食べる必要はありませんが、消化の良いものを少しずつ食べるようにしましょう。 おかゆ、うどん、スープなどがおすすめです。
- 部屋の換気: 定期的に部屋の換気を行い、空気を入れ替えましょう。
- 湿度管理: 部屋の湿度を50~60%に保つようにしましょう。 加湿器を使うか、濡れタオルを干すなどして、湿度を調整しましょう。
- マスク着用: 家族や同居人に感染を広げないために、マスクを着用しましょう。
- 手洗い: こまめに手洗いを行い、ウイルスの拡散を防ぎましょう。
解熱剤の使用
インフルエンザの際に、解熱剤を使用する場合は、注意が必要です。 アセトアミノフェン以外の解熱剤(アスピリンなど)は、インフルエンザ脳症のリスクを高める可能性があるため、使用を避けましょう。 解熱剤を使用する場合は、医師や薬剤師に相談し、適切な種類と量を使用するようにしましょう。
インフルエンザの予防法
インフルエンザは、予防が何よりも大切です。 以下の予防策を実践し、インフルエンザから身を守りましょう。
予防接種
インフルエンザの予防接種は、インフルエンザの発症を予防し、重症化を防ぐ効果があります。 予防接種の効果は、接種後2週間程度で現れ、約5ヶ月間持続します。 毎年、流行するウイルスの型に合わせてワクチンが作られるため、毎年接種することが推奨されます。
予防接種を受ける時期
インフルエンザの流行は、通常12月下旬から3月頃までです。 そのため、予防接種は、10月から12月中旬までに受けるのが理想的です。
手洗い、うがい、マスク
インフルエンザウイルスは、飛沫感染や接触感染によって感染します。 そのため、手洗い、うがい、マスクの着用は、基本的な感染予防策です。
- 手洗い: 石鹸と流水で、30秒以上かけて丁寧に洗いましょう。 特に、外出後、食事前、トイレの後、咳やくしゃみをした後などは、必ず手洗いをしましょう。
- うがい: 水やうがい薬で、15秒以上かけてうがいをしましょう。 うがいは、のどに付着したウイルスを洗い流す効果があります。
- マスク: 不織布マスクを正しく着用しましょう。 マスクは、飛沫の拡散を防ぎ、ウイルスの吸入を減らす効果があります。
湿度管理
インフルエンザウイルスは、乾燥した環境を好みます。 そのため、室内の湿度を50~60%に保つようにしましょう。 加湿器を使うか、濡れタオルを干すなどして、湿度を調整しましょう。
免疫力を高める生活習慣
免疫力を高めることは、インフルエンザだけでなく、様々な感染症の予防につながります。 以下の点に注意して、免疫力を高める生活習慣を心がけましょう。
- バランスの取れた食事: 栄養バランスの取れた食事を、1日3食規則正しく食べましょう。 特に、ビタミンC、ビタミンD、亜鉛などの栄養素は、免疫力を高める効果があります。
- 十分な睡眠: 睡眠不足は、免疫力を低下させます。 毎日、7~8時間の睡眠時間を確保しましょう。
- 適度な運動: 適度な運動は、血行を促進し、免疫力を高めます。 ウォーキングやジョギングなど、無理のない範囲で運動を続けましょう。
- ストレスの軽減: ストレスは、免疫力を低下させます。 趣味やリラックスできる時間を持つなどして、ストレスを軽減しましょう。
インフルエンザに関するQ&A
ここでは、インフルエンザに関するよくある質問にお答えします。
Q: インフルエンザにかかったら、学校や会社は何日休むべき?
A: 学校保健安全法では、インフルエンザの発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで、出席停止と定められています。 会社の場合は、法律で定められていませんが、学校保健安全法に準じて、休む期間を決めるのが一般的です。
Q: 妊婦や授乳中の女性は、薬を飲んでも大丈夫?予防接種は受けてもいい?
A: 妊婦や授乳中の女性は、インフルエンザにかかると重症化するリスクが高いため、予防接種を受けることが推奨されます。 また、抗インフルエンザ薬は、医師の判断のもとで、服用することができます。 妊娠中や授乳中の場合は、必ず医師に相談し、指示に従いましょう。
Q: インフルエンザの予防接種は毎年受けるべき?
A: インフルエンザウイルスは、毎年少しずつ変異するため、前年に接種したワクチンの効果が、翌年には十分でない場合があります。 そのため、毎年予防接種を受けることが推奨されます。
Q: 家族がインフルエンザになったら、どうすればいい?
A: 家族がインフルエンザになった場合は、以下の点に注意して、感染を広げないようにしましょう。
- 患者の隔離: 可能であれば、患者を個室に隔離し、他の家族との接触を避けましょう。
- マスク着用: 患者だけでなく、看病する家族もマスクを着用しましょう。
- 手洗い: こまめに手洗いを行い、ウイルスの拡散を防ぎましょう。
- 換気: 定期的に部屋の換気を行い、空気を入れ替えましょう。
- 消毒: 患者が触れたもの(ドアノブ、手すり、トイレなど)は、消毒液で拭きましょう。
- 予防内服: 医師に相談し、抗インフルエンザ薬の予防内服を検討しましょう。
Q: インフルエンザの最新情報はどうやって入手できる?
A: インフルエンザの最新情報は、以下のサイトで確認することができます。
- 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/
- 国立感染症研究所:https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-map.html
- 各自治体の保健所
まとめ
インフルエンザは、風邪とは異なり、重症化するリスクもある感染症です。 しかし、正しい知識を持ち、適切な対策を講じることで、感染のリスクを減らし、重症化を防ぐことができます。
この記事では、インフルエンザの症状、検査、治療、予防法について詳しく解説しました。 ぜひ、この記事を参考に、インフルエンザから自分と大切な人を守りましょう!
- インフルエンザは、風邪と比べて症状が重く、急激に発症するのが特徴です。
- 高熱、関節痛、筋肉痛、倦怠感などの症状が出たら、早めに医療機関を受診しましょう。
- インフルエンザの検査は、迅速診断キットを使えば、短時間で結果がわかります。
- インフルエンザの治療には、抗インフルエンザ薬が有効です。発症後48時間以内に服用を開始することが重要です。
- インフルエンザの予防には、予防接種、手洗い、うがい、マスク、湿度管理、免疫力アップが効果的です。
もし、インフルエンザにかかってしまった場合でも、慌てずに適切な対処が大切です。
風邪とインフルエンザとコロナの判断は自分でせず、医療機関でみてもらい、適切な薬の処方等をしていただくことが重要です。


![【母の日はいつ】日付の由来、世界各国の母の日、プレゼント選びのヒントまで徹底解説[2025年最新版]](https://mokuteki.net/wp-content/uploads/2025/02/1742299516-f38c530fff06434c5f84003d3f0bcb75-720x393.png)